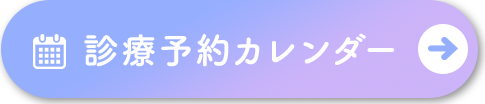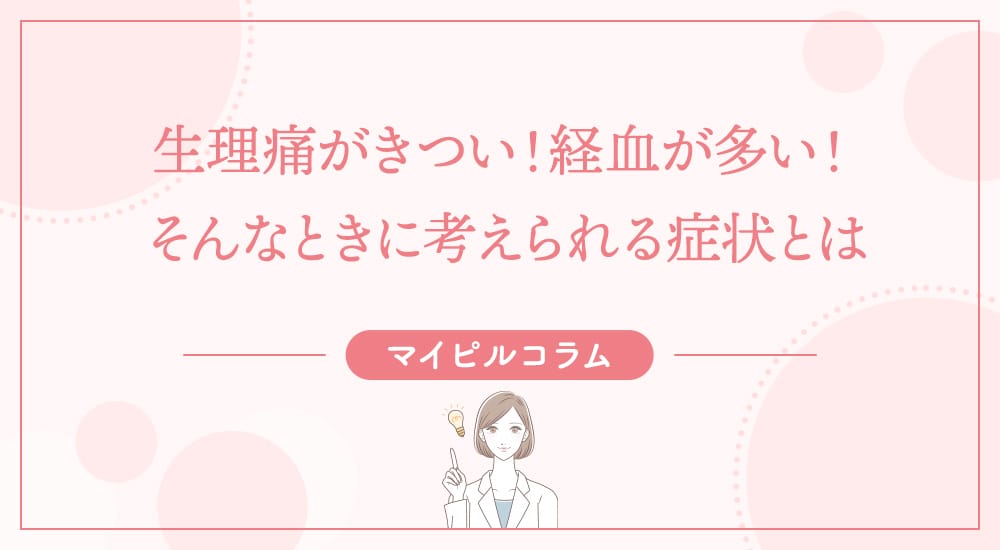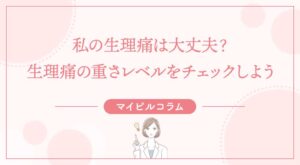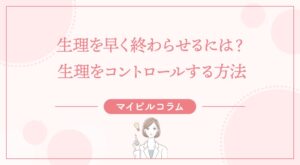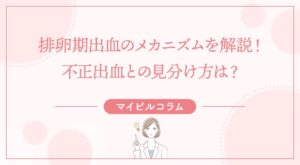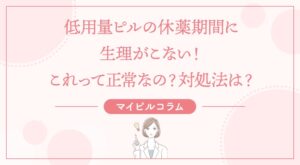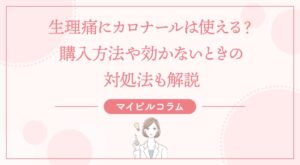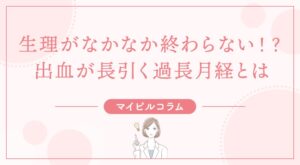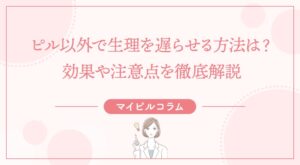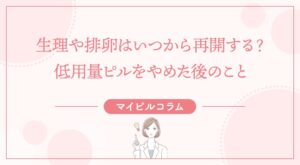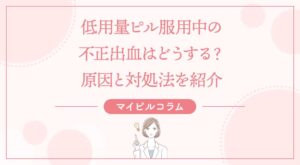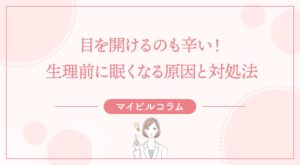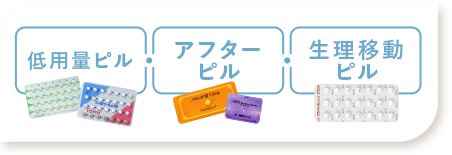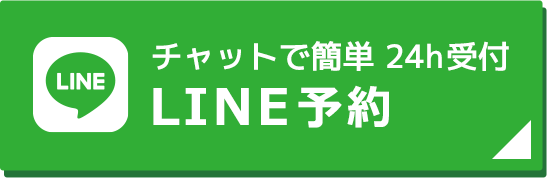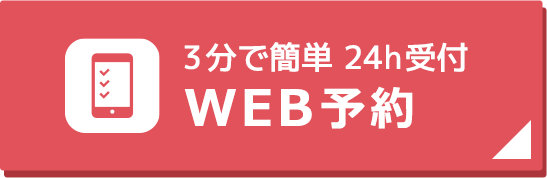私の生理痛は大丈夫?生理痛の重さレベルをチェックしよう
「生理のときに経血量が多いのが気になる」
「経血量が多いのは体に何か問題があるの?」
経血量が多いと、異常があるのではと不安に思う方が多いのではないでしょうか。生理は健康のバロメーターとも呼ばれていることから、経血量が健康状態を示す場合もあります。
経血量が多い場合は病気の可能性もあるので注意が必要です。今回は、生理の経血量が多いときに考えられる病気や治療法を詳しく解説します。
生理の経血量が多いときは月経過多の可能性がある
生理の経血量が多いときは、月経過多になっているかもしれません。日本産婦人科医会では、正常な生理の経血量を20~140gとしています。
1回の生理期間の経血量が140gより多い場合は月経過多です。逆に20gより少ない場合は過少月経となります。
月経過多かどうかを判断する方法
経血量が140gより多いと月経過多となりますが、経血量を正確に計るのは簡単ではありません。経血量が多いとは感じていても、具体的にどれくらいの量なのか把握している方はほとんどいないでしょう。次のような場合は、月経過多の可能性があります。
- 日中でも夜用のナプキンを使わないと漏れてしまう
- ナプキンやタンポンをつけても1時間も経たずに漏れてしまう
- 経血量が多いと感じる期間が8日以上続く
- 500円玉サイズ以上のレバー状の塊が出る
日中でも夜用ナプキンが必要な場合は、平均よりも経血量が多いと考えられます。経血量が正常であれば、通常は日中に夜用ナプキンをつける必要はありません。
ナプキンやタンポンが1時間もたない方も経血量が多いといえます。経血量が多いと感じる期間が8日以上続く方、500円玉サイズ以上のレバー状の塊が出る方も月経過多の可能性があるでしょう。
生理の経血量が多い月経過多で考えられる病気
生理の経血量には個人差があります。量が多少多くても問題ないケースもありますが、中には病気が隠れていることもあるので注意しましょう。月経過多となる病気には、以下のようなものがあります。
- 子宮筋腫
- 子宮内膜症
- 子宮腺筋症
- 黄体機能不全
- 無排卵性周期症
- 甲状腺機能異常
- フォン・ヴィレブランド病
子宮筋腫
子宮筋腫は、子宮を構成する平滑筋と呼ばれる筋肉にできる良性の腫瘍のことです。30歳以上の女性の20~30%で見られます。経血量が多くなり、生理痛があらわれやすくなることが特徴です。
無症状の場合、特に治療は必要ありません。しかし、経血量の増加や生理痛、不妊や習慣流産など症状がある場合は手術や薬などを使った治療が必要です。
子宮内膜症
子宮内膜症は、子宮内膜やそれに似た組織が子宮内膜以外の場所にできる病気です。20~30代の女性で多く見られます。
代表的な症状は生理痛と不妊ですが、月経過多の症状が見られることも珍しくありません。不妊や流産のリスクも高めてしまうため、早期発見と早期治療が大切です。
子宮腺筋症
子宮内膜と似た組織が子宮平滑筋の中にできる病気です。子宮腺筋症が起こる原因はまだ分かっていません。生理痛や経血量の増加が主な症状です。子宮内膜が分厚くなったり子宮筋腫ができたりすることもあります。
黄体機能不全
黄体機能不全とは、黄体ホルモン(プロゲステロン)の分泌量が不十分な状態のことです。排卵後に作られる黄体が正常に働かず、黄体ホルモンの量が不足します。こちらも原因は詳しく分かっていません。受精卵が着床しにくくなるため、不妊の原因にもなります。
無排卵性周期症
無排卵性周期症とは、生理のような出血があるものの排卵が起こっていない状態のことです。放置しておくと、卵巣の機能が次第に衰えて不妊や早期閉経につながることがあります。経血量が増えたり生理周期が乱れたりなどの症状が見られることが特徴です。
甲状腺機能異常
甲状腺ホルモンの分泌量が多すぎる甲状腺機能亢進症、甲状腺ホルモンの分泌量が少なすぎる甲状腺機能低下症になると、月経過多や生理不順などの症状が見られることがあります。
フォン・ヴィレブランド病
フォン・ヴィレブランド病は、出血性の病気です。遺伝性で、男女とも同じ割合で見られます。出血しやすくなるため、女性では月経過多や生理期間の延長が見られます。患者数は100人中約1~2人程度です。
生理の経血量が多い月経過多の治療法
生理の経血量が多い場合、治療によって量を正常に戻せる可能性があります。病気がある方は、病気の症状に合わせた治療を受けることが大切です。
低用量ピル
生理期間中に強い生理痛が起こったり腹痛や腰痛が見られたりする場合は、月経困難症の可能性があります。月経困難症の治療に有効なのが低用量ピルです。
2種類の女性ホルモンを配合した飲み薬で、服用するとホルモンバランスを一定に保てます。子宮内膜症や子宮腺筋症などの治療にも用いられます。
黄体ホルモン製剤
黄体ホルモン製剤は、低用量ピルとは違って黄体ホルモンのみしか配合されていません。生理そのものを止める働きがあるため、月経過多の治療に効果があります。
この他、ミニピルも黄体ホルモンのみが配合された飲み薬です。こちらも月経過多を改善する効果があります。
GnRHアンタゴニスト製剤
GnRHアンタゴニスト製剤は、子宮内膜症や子宮筋腫などの治療に用いられる薬です。強制的に閉経状態を作り出すため、人によっては生理がこなくなることがあります。
GnRHアゴニスト
GnRHアンタゴニストが出る前はGnRHアゴニストがよく使われていました。
偽閉経療法という、女性ホルモンのエストロゲン分泌を抑え、子宮内を閉経に近い状態にすることで、子宮筋腫や子宮内膜症などを治療する方法です。
ダナゾール製剤
子宮内膜症の治療に用いられる薬です。下垂体や卵巣、子宮内膜の組織に働きかけて子宮内膜やそれに似た組織が増殖するのを抑えます。
ミレーナ
ミレーナは、レボノルゲストレルという女性ホルモンを子宮内で5年間放出し続ける子宮内黄体ホルモン放出システムです。もともとは避妊システムとして用いられていましたが、現在は過多月経治療薬として承認されており、保険も使用できます。
手術療法
月経過多の原因となる子宮筋腫や子宮腺筋症がある場合は、手術で取り除く場合もあります。手術に抵抗がある方、子宮を残しておきたい方のために、マイクロ波子宮内膜アブレーション(MEA)も行われるようになってきました。こちらはマイクロ波を使って子宮内膜を焼く治療法です。
生理の経血量が多い状態を放置しておくリスク
経血量が多い状態を放置しておくと、「貧血」や「不妊症」のリスクが高まります。
貧血になる
経血量が多いと、その分だけ血液と共に鉄分も失われることになります。そのため、月経過多の方は貧血に注意しなければなりません。1周期あたりの経血量が80ml以上ある女性のうち、約3分の2で貧血が見られるといわれています。
不妊症につながる
月経過多を引き起こす子宮内膜症や子宮筋腫、黄体機能不全などを放置しておくと不妊症になる可能性があります。不妊症のリスクを最小限にするためにも、月経過多の症状があるときは早めに婦人科を受診しましょう。
生理で気になることがある方はマイピルへ
マイピルは、オンライン上で産婦人科医による診療を受けられるサービスです。生理について少しでも気になることがあればいつでもマイピルにご相談ください。
小さな悩みも産婦人科医が回答
どんなに小さな悩みでも構いません、マイピルでは、「経血が多い気がする」「生理痛がつらい」など、女性ならではの悩みに対して親身に対応しています。どのような悩みでも産婦人科医が直接担当しているので安心してご利用ください。
電話1本で診療を受けられる
産婦人科や婦人科の受診に抵抗がある方でも、マイピルなら電話1本で診療を受けられます。電話がつながる場所ならどこからでも診療を受けることが可能です。
処方された薬は自宅までお届け
薬が処方された場合は、最短翌日に自宅までお届けします。品名は「サプリメント」と記載しているので、ご家族に中身がバレる心配はありません。また、郵便局留めやクロネコヤマトセンター留めもご利用できます。
まとめ
生理痛がきつい、経血量が多いときは月経困難症や月経過多の可能性があります。経血量が140gより多いときは月経過多です。月経過多を放置しておくと貧血や不妊症のリスクが高まるため、早めに産婦人科や婦人科を受診しましょう。
日中も夜用ナプキンを使用している、ナプキンやタンポンが1時間もたないなどがある場合は、月経過多の可能性が高いと考えられます。
マイピルでは、症状に応じて低用量ピルの処方を行っています。生理で気になることがあれば、お気軽にご相談ください。